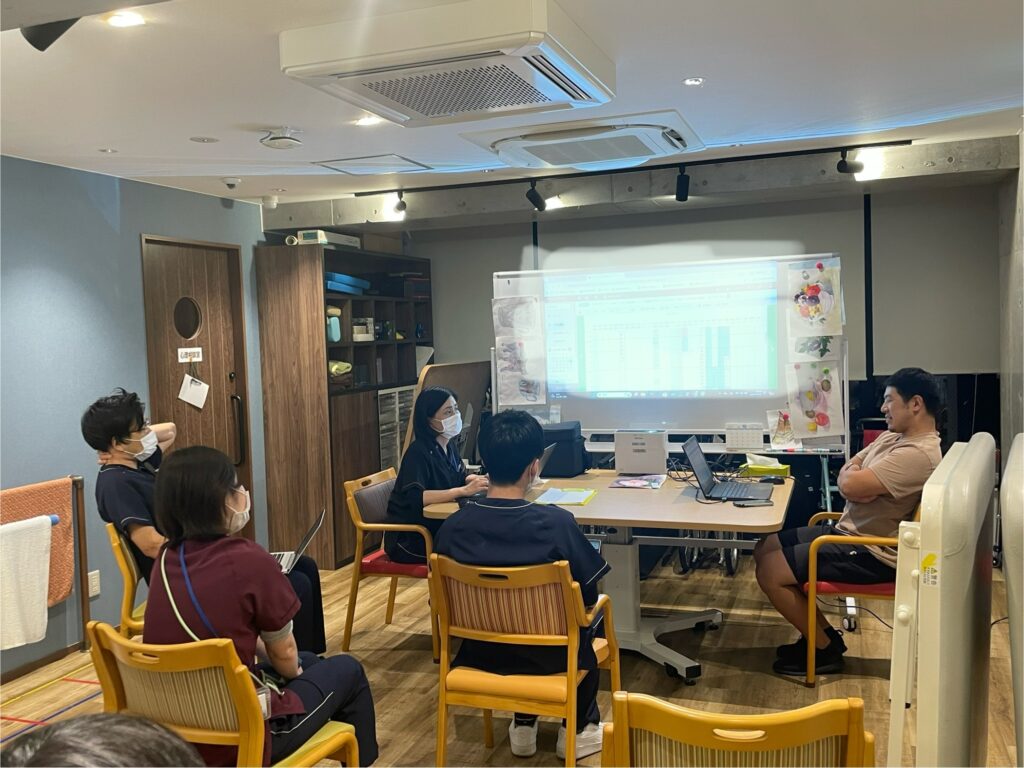医療コラムvol.9『歩行速度の低下を感じたら…』
リハビリテーション部医療コラムvol.9です。 今回は、『歩行速度の低下を感じたら…』についてお届けいたします。
「街を歩いていて、周りの人に抜かされてしまう・・・」「信号が青のうちに横断歩道を渡りきるのが大変・・・」
「駅まで歩くのに、以前より時間がかかるようになった・・・」などと感じたことはありませんか?
歩行速度は重要な運動指標です
歩行速度は重要な運動指標であり、国立長寿医療研究センターでは、歩行速度と要介護の関連性についての研究もされています。フレイルやサルコペニアの診断基準にも歩行速度が含まれており、通常歩行速度が1.0m/秒未満だと該当すると言われています。横断歩道は、一般的に1.0m/秒で歩くと渡り切れるように設計されているそうです。
歩行速度は「距離÷時間」で求められ、当院では距離を決めてそれにかかる時間を測定する方法で歩行速度を測定しています。リハビリテーションの場面では、歩行速度とともに、歩数や歩幅、歩行率(歩数÷時間)、姿勢なども評価して歩行速度の低下の原因を探ります。
では、歩行速度の低下には具体的にどのような原因が考えられるでしょうか。
歩行速度の低下の原因
◎加齢により筋肉量が減少すること(サルコペニア)。
◎関節痛や運動不足により関節の変形や可動範囲の狭小化が生じること。
◎疾患の症状に伴い運動機能の低下が生じること。
・脳卒中による片麻痺、感覚障害、運動失調などの症状。
・パーキンソン病による小刻み歩行、すり足などの症状。
・脊柱管狭窄症などの整形外科疾患や糖尿病などによる末梢神経障害。
◎呼吸循環器疾患に伴い心肺機能の低下が生じること。
◎視覚および聴覚機能の低下が生じること。
他にも…
靴や歩行補助具、認知機能や精神機能なども歩行速度の低下に関連しており、複数の原因が影響していることも多く、これらの原因が歩幅の狭小化やバランス能力の低下をきたし、歩行速度の低下に繋がります。
原因を特定し、それに応じた治療やリハビリテーションが重要です。
当院では、歩行速度低下外来を開設し、脳神経内科、脳神経外科、整形外科、呼吸器内科といった様々な方面から原因を追求するとともに、リハビリテーション治療を行っております。お心当たりのある方はぜひ一度受診をご検討ください。